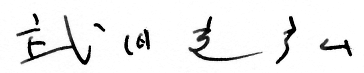TOPページへ戻る
![]()
武田光弘 第1回個展開催に当たって
巴里/冬・春・夏・秋
2004年5月11日(火)~5月22日(土) Color Museum
色彩美術館
東京都
渋谷区神宮前6-25-8-810
冬のサーカス 武田光弘
とうとうパリに来てしまった。冷たい雨が降っている。モンマルトルの坂道に、枯葉が散って濡れている。明日から、何が僕を待ち受けているのだろう-----。(2002.11.10記)
僕がはじめてパリを訪れたのは、1971年の春だった。あれから30年以上の歳月が流れた。きっといつかあの街に住み、絵を描いて暮らそうと、心のどこかで思い続けていた。絵を描くということは、僕にとっては特別な意味を持っていた。それは、物心ついたときから、心の奥深いところに在る“僕のもともとの世界”とでも言うべきものだった。今何をしていようが、何処にいようが、いつかはきっとそこへ行くのだと思っていた。パリは、そのことのために、もっともふさわしい場所だった。
パリの冬は、暗く底冷えがして、冷たい小雨が降り続く。初めの1か月は、モンマルトルのホテルに住んだ。12月になって、サン・マルタン運河に近い、レビュプリックのアトリエに移った。モンパルナスのアカデミーにも通い始めた。しかし、僕の気持ちはどこか重く、気が晴れないのだった。僕は、スケッチブックを持って、暗いパリの冬空の下を、ひたすら歩き廻った。モンマルトルの丘からマレ、バスチーユ、カルチェ・ラタン、サン・ジェルマン・デ・プレ。セーヌの風は冷たく、筆を持つ手は凍え、しょっちゅうカフェに飛び込んだ。デパートのトイレの場所は全部覚えた。スケッチの数は増えていったが、心と体は何故か冷え切っていた。僕は今何をしているのだろうと思った。 ある夜、家からそう遠くない一角を歩いていると、突然目の前に、煌々と輝く大きな建物が現れた。赤い看板にはCIRQUE D'HIVERと書かれていた。“冬のサーカス”。いい言葉だと思った。そして、これはまさに、僕のための言葉だと思った。
そんなある日、リュクサンブール公園で、一人の日本人画家と知り合った。パリに長らく住み、70歳を越えているというその方は、今も毎日外に出て、絵を描き続けているという。画家は僕の絵を見て、あなたは天性のものを持っていると言った。その後もこの方は、終始僕の絵を褒め、元気付けてくれたのだった。僕は父の言葉を聴いているような気がした。 父は、僕が2歳のときに亡くなったが、画家だった。父が残したスケッチの数々、ヨーロッパから取り寄せた美術全集、フランスの小説本。僕はこれらの遺品の中に、父の言葉を聴き、会話をして育ったのだった。 画家は山本 平さんといったが、僕はあちこちの写生に同行するようになった。 いつの間にか心は軽くなり、暗い空は遠のいていった。
パリの春は、ある日突然やってくるという。3月半ばを過ぎた日曜日。僕は、東京から来た友人夫妻と、ルーブル美術館に近い、パレ・ロワイヤルの中庭を歩いていた。すると何かが違うことに気付いた。よく刈り込まれて、天を刺す黒い棘のようだった樹々の梢が、ほのかに黄色味を帯びて、いつの間にか優しくなっているのだ。見渡すと、先の方には薄紫の木蓮がほころびかけているではないか。そうか、今日だ。今日、パリに春が来たのだと思った。あの長く暗い冬が去って、マロニエが花咲き、プラタナスの若葉が陽光に輝く、パリの春がやって来たのだ。復活祭も近いが、キリストと共に甦るのは、実は僕たち自身なのだと思った。住んで初めて知った、春を迎える喜びだった。
パリは歩く街だ。メトロは便利で速いが、バスの方がずっといい。街が見えている。気に入った風景があるとすぐ降りて歩く。パリには20の区があるが、僕はそのほとんどを歩いた。何処で描いていても誰も気にしない。たまに立ち止まって絵を見る人がいる。「お前は絵描きか?」「ウイ」。それだけだ。ニコッと親指を立てて通り過ぎる。 セーヌ。そこに架かる橋たち。ゆったりと流れる水。吹き過ぎる風。ペール・ラシェーズ、モンマルトル、モンパルナス墓地の静止した時間。ベルヴィルの丘から見る夕焼け。ヴァンセンヌ、ブー口ーニュ、モンスリ公園の小径と花々----。すべてのことが遠ざかっていった。僕は独りで、自由だった。パリの風に吹かれ、時を忘れて、ただひたすら絵を描いていたのだった。季節は夏となり、コート・ダジュール、プロヴァンス、ノルマンディ、そしてブルゴーニュからベルギーへと、僕のスケッチの旅も広がっていった。
人は本当に無私のものに出会えるのだろうか。全てを捨ててもいいもの、お金や、評価とは関係なく、それだけで満足できるもの。絵は、果たして僕にとって、唯一で無私のものといえるのだろうか---。確かに、朝から絵を描いていて、気付いたら外が暗くなっていたこともある。絵を描くということは、何かと出会い、何かを発見していくことだ。だから感動し、心がときめくのだ。しかし、その一方で、自分の形や色が見つからずに、自分のアイデンティティがばらばらになっていく恐怖も味わった。目の前には暗い闇だけが広がっているように思った。才能への思い込みと現実との狭間で、心が揺れ動くのだ。 いつの間にか日が短くなり、マロニエが色づき、散り始めていた。
帰国の日が近づいたある夜、僕は外出から戻って、アパルトマンの中庭を歩いていた。小雨が音もなく降っていて、暗い空から落ちてくる小さな雨粒たちが、窓から漏れる光に照らされて、美しく幻想的だった。僕はそのときふと、雨粒たちが“時間の粒子”のように思えた。見上げる僕の顔に“時のこどもたち”が触れていく中を、僕は通り過ぎて行く。時が過ぎて行くのではなく、時の中を、僕が通り過ぎて行くのだと思った。 そうなのだ。お前はこうして無心に歩いて行けば良いのだ。ただ前に向って---と思った。
---僕を乗せたパリ発ANA206便は、家族が待つ東京へ向かって、天空を飛んでいる。366日ぶりの再会だ。この先に待っているものにも、勇気を持って、真直ぐに向かって行こう。 新しい旅は、まだ始まったばかりなのだ。
(2003.11.11機上にて)
御礼のご挨拶
初夏の候、益々ご清栄のことと存じます。このたびはご多用の中を、私の個展にご来駕賜りまことに有難うございました。また、暖かいお志とお励ましを頂戴し、恐縮いたしております。あわせて10日間の会期中に、およそ400人の方々にお出でをいただきました。せっかくご来場を賜りながら、十分なおもてなしもご挨拶も出来ずに、失礼を申し上げた方々もいらっしゃることと思います。あらためてお詫び申し上げます。思いがけない沢山のお花や、頂戴しましたお品物に囲まれて、今もまだ呆然とし、気の抜けたようになっております。そして、お書きくださったご感想を何度も読み返しながら、身の引き締まる思いと共に、感動とうれしさがこみ上げてまいります。
「絵とむきあった瞬間、描く喜びが画面から伝わってきて、魂がふるえました」というお言葉を読んで、言葉に出来ないほど感激し、私こそ感動で心がふるえました。私の勝手な生き方と、拙い作品にこれほどの暖かいお気持ちをいただけるとは、夢にも思っていませんでした。66歳の今日まで、これほどの皆様にご迷惑をおかけし、またおカ添えを賜ってきたのだということを、あらためて肝に銘じながら、皆様に心から感謝を申し上げます。
帰国して以来、身辺に些事が続き、絵もほとんど描いておりませんが、長い道のりがまだ始まったばかりです。プロでもアマでもない一人の画家として、パリで過ごした日々のように、今後もゆっくりと、無心に、絵を描いて生きたいと考えています。またいつか皆 様に作品をご覧いただく日を夢見ながら---。
本当に有難うございました。皆様のご自愛を心よりお祈り申し上げます。
2004.5.24